連休はどう過ごされましたか? 連休明けも、暑く、そして時に激しい雨だったりと、過ごしにくい日々が続いています。
私はクリニックが休診している間はずっとクリニック内で、自分が講演する内容のスライドを作り、論文をよみ、間違いが無いか吟味し、自身の新しい考え方や、聴衆される方が飽きないような工夫も施していました。 お墓参りもせず、ずっと机(パソコン)にしがみついていました。 ご先祖様には申し訳ないと思う次第でした。
さて、健診結果が悪かったといって、その結果を持ってきてくださる患者様がおられ、結果をみてみると、「心肥大あり」と書いていますが、「心電図は異常なし」と書かれています。 ここまで読んで、「書いた医師が勘違いをしているな」と思われる方は相当の医療通です。 心肥大は「心電図」か「心エコー検査」でしか判断できないはずだからです。 一般的な健診では心エコーはされていませんし、レントゲンで分かるのは「心拡大」だけです。 つまりレントゲンと心電図を組み合わせて、「心拡大」+「心肥大』はありえるのですが、心電図が正常な心肥大はありえません。 ひょっとすると、患者さんを左側臥位(左側を下にして寝てもらう)にして、聴診器でIV音を聴いたか、心尖拍動を二峰性にふれているなら話は別ですが… そんな記載も無く、身体所見は「特記すべき事項なし」でした。
レントゲンでは、どこからどこまでが、心臓の筋肉部分で、内腔の血液部分との差が分からないので、筋肉が肥大しているかどうかは分からないのです。 ちなみに(造影剤を使わない普通の)CT検査でも貧血が無い限りなかなか分かりません。 CT検査で、心筋部分と血液部分が分かった場合は、「貧血あり」と判断出来ます。 これは私が放射線科で1年間研鑽を受けて理窟も教えてもらったのでそういうことが言えます。
間違った健診結果だったとしても、「心肥大」「心拡大」が書かれた場合は、私などの超音波専門医が直接心エコーをし、原因をつきとめ、治療が必要かどうか、経過観察で良いのかどうかを判断します。
以前、「循環器クリニックのキモは、心エコーは専門かどうか」と書いたのはそういった意味もあります。
大きな病院(私の場合は、現:四国こどもとおとなの医療センター)で、最終的なチェックを行っていたような専門性がないと、同じお金を出して検査をしても、悪い言い方ですが「いい加減」な心エコー検査を行われる可能性が高い、と思います。 自戒の念を込めて、来月、心エコーの講演会を高松で行います。 開業医こそ、本でみるだけ、ではなく、講演会での聴講はもちろん、自分から情報を発信できるようにならないとレベルはどんどん下がっていくことに繋がると思い、連休は連休とならなかったわけです。
※しかし、人の命を預かる医師が、普通の企業人と同じ休みを取ることは、私の中ではありえない、と思っています。 私と同年代の医師は、中・大病院で夜も寝ずに診療しています。 それに比べれば、私の仕事量は足りませんし、緊急性を要することもありません。 医師という仕事は、いつになってもサボった時点で駄目な職人芸です。 サボった医師は、だいたい分かります。 なので、そういう医師への紹介は私はしませんでしたし、今も、大きな病院でも、「ちゃんとした」病院を選んで紹介しています。


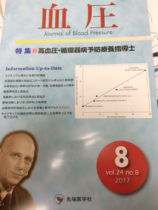 皆様よろしくお願い致します。
皆様よろしくお願い致します。